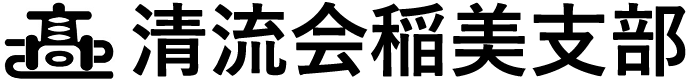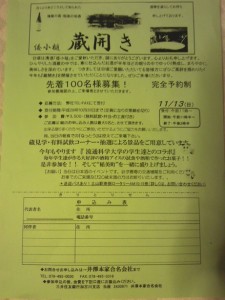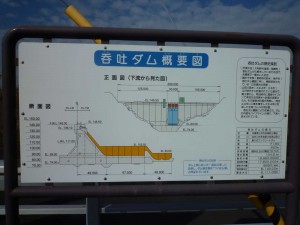-

【お知らせ】第29回清流会稲美支部総会について
清流会稲美支部の皆様こんにちは。 今回は毎年年一回開催されます清流会稲美支部総会のお知らせです。 お忙しいところ申し訳ありませんが、ご参加よろしくお願い致します。 日時:平成29年5月7日(日)午前10時~ 場所:稲美町立コミュニティーセンター(... -

清流会稲美支部 第4回ウォーキング「寺家町通りから日毛社宅群、泊神社へ」(加古川市)
稲美支部のウォーキング実施日は11月23日(祝)と決められている。 予定が立てやすいこと、好天に恵まれる可能性が高いこと等が理由である。 第1回「播州葡萄園跡と葡萄園池を訪ねて」、第2回「東二見から住吉神社への遊歩道」、第3回「湯の山街道の町... -

清流会稲美支部ウォーキング 「東播磨の歴史を訪ねて(第4回)」 参加者募集!
東播磨、とりわけ加印地区は印南野という名で風土記・万葉集の時代から風光明媚な場所として知られています。 せっかくその地に生まれ育ったのだから身近にある史跡や風景に親しもうと、三年前の秋、清流会稲美支部では 播州葡萄園跡・葡萄園池・井澤本家... -

東北の復興3
~未来予想図~ 大都市以外は地方と呼びましょう。 どこも消滅可能性自治体です。 防潮堤などの工事が終了する数年後、いったい東北を含む地方はどうなっているのでしょう。国道6号線を走るとわずか200mの区間に3軒パチンコ店があります。数年後、全国か... -

【お知らせ】11月13日(日)井澤本家 蔵開き!
皆さま、こんにちは。 今年も『井澤本家 蔵開き』の季節がやってまいりました。 日時は、11/13(日)午前11時半~午後2時半まで(受付11時~) 参加費は、¥3,500-(無料試飲、弁当、お土産付き) 先着100名様募集!です。 ★今年もやります『流通科学大学... -

東北の復興2
~仙台をマチブラして~ 東北一の都市、杜の都(もりのみやこ)仙台は兵庫でいうと神戸に匹敵する大きな街で、歓楽街の国分町(通称:ブンチョウ)は三ノ宮の倍くらいの規模です。 すべての道はローマに通ずるがごとく、何をおいてもSENDAI・センダ... -

東北の復興1
東高OG・OBの皆様、こんにちは。 「会いたい先輩・輝く先輩」です。 広報いなみ9月号に、宮城県山元町の齋藤俊夫町長が稲美町長を表敬訪問された記事が掲載されていたことをご存知ですか? 稲美町では、2011年3月に発生した東日本大震災の復興支援のために... -

(お知らせ)第28回清流会稲美支部総会について
清流会稲美支部の皆様こんにちは。 今回は毎年年一回開催されます清流会稲美支部総会のお知らせです。 お忙しいところ申し訳ありませんが、ご参加よろしくお願い致します。 【日時】 7月3日(日) AM10:00~ 【場所】 稲美町立コミュニティー... -

清流会稲美支部 第3回ウォーキング「湯の山街道の町並みと三木城址」(三木市)
やや雲があるものの、風もなく穏やかな日差しの平成27年11月23日(祝)、清流会稲美支部の第3回ウォーキングが開催された。稲美中央公園に集まった参加者には、第1回の「播州葡萄園跡と葡萄園池を訪ねて」、第2回の「東二見から住吉神社への遊歩道」の... -

稲美町のトマト4
トマトは、ナス科ナス属です。 病気に対して強くなるように接ぎ木苗を使用しているそうです。 トマトには、ナスの台木を用いるそうです。 その他に、畠農園ではロックウール栽培も行っています。 ロックウールとは、天然岩石などを高温で溶かした後に繊維...